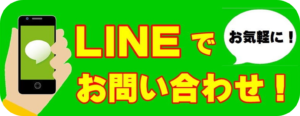過食症とは

過食症は、
「短期間に大量の食べ物を摂取し、その後に強い罪悪感や無力感を感じる」
という、「摂食障害」の一種です。
ストレスや感情の変化、ホルモンバランスの乱れが原因として挙げられます。
発症の背景には、心理的要因だけでなく、
腸内細菌やホルモンが関与する「腸脳相関」の乱れも注目されています。
食欲を調節するホルモンが正常に働かなくなることで、
満腹感を得られにくくなり、過食を繰り返してしまう傾向があります。
治療や予防には、 身体的・心理的なアプローチのほか、腸内環境の改善も重要です。

腸内細菌との関係
腸内細菌は、私たちの食欲や代謝に密接に関わっています。
腸と脳が互いに影響し合う「腸脳相関」を通じて、
腸内細菌が食欲を制御するホルモンの分泌に影響を与えることが分かっています。
特に、脂肪細胞から分泌されるホルモン「レプチン」は、
満腹感を伝える重要な役割を果たします。
しかし、腸内環境の乱れにより、レプチンの働きが低下すると、
過食を引き起こしやすくなります。
また、過食症の発症機序として、腸内細菌バランスの崩れが挙げられます。
特に悪玉菌が増えると、
腸内での短鎖脂肪酸の産生が低下し、
腸脳相関が乱れることで食欲の制御が難しくなる可能性があります。

対策
対策として、
水溶性食物繊維や
プロバイオティクス(善玉菌を含む食品)を
積極的に摂取することが有効とされています。
水溶性食物繊維は、
腸内細菌のエサとなり、
善玉菌を増やして
腸内環境を整えるプレバイオティクスの役割を果たします。
また、プロバイオティクスを組み合わせることで、
腸内で短鎖脂肪酸が産生され、食欲制御や代謝改善が期待されます。

【重要】
このブログの内容は、ネット上の記事や書籍の抜粋&意訳を元にした個人の感想・戯言であり、なんら特定の物の効能・効果を示すものではありません。