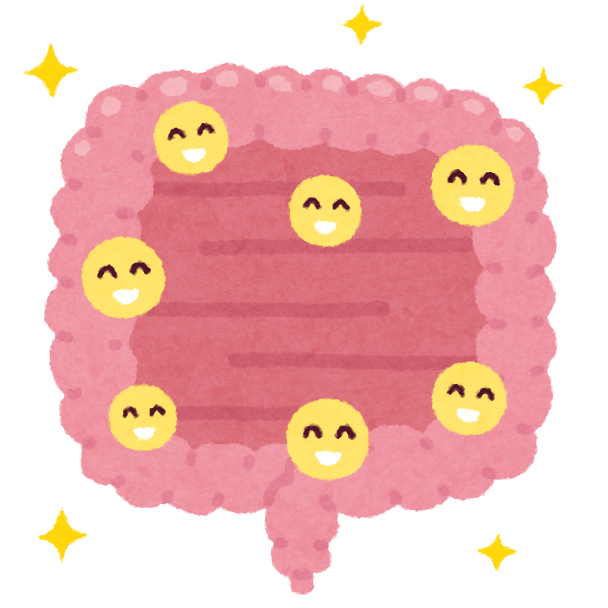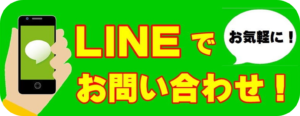腸活してますか?
毎日のようにテレビ・雑誌などで「腸」と様々な症状の関係がとりざたされていますが、わたくし自身、アトピーと腸の関係は実体験もしているのでとても興味深いものです。
そこで、腸といろんな症状について、めちゃめちゃわかりやすくまとめていただいている本があったので、さまざまな不調や病気別に腸とのつながりと対策を「勉強してみた!」
すごく簡潔にまとめられていますので、だいたいの「流れ」としてご覧ください。
最初は、【対策】の部分をすっ飛ばして読むと「流れ」がわかりやすいかもしれません。
(「新しい腸の教科書」江田証先生著より)
じゃ、いってみましょー!(長いです。)
- 便秘(運動不足や強いストレスで、腸の動きが「低下」!)
- 下痢(腸の動きが「過剰」に活発になって、水分吸収が不十分に!)
- 食欲不振(ストレスや腸の不調が、満腹中枢を刺激!)
- 肥満(「太らせ薗」の増殖で、栄養素を過剰に吸収!)
- 生理痛(腸内環境の悪化と女性ホルモンの分泌低下!
- 肌荒れ(悪玉菌増加で有害物質が肌に蓄積!)
- むくみ・冷え性(悪玉菌の増加によって血行不良が発生!)
- 腰痛(腸管神経のSOSが周辺筋肉を緊張させる!)
- 肩こり(腸のSOSが不良姿勢を招いて肩の負担増!)
- 不眠(腸内の不調が自律神経を乱し、睡眠を妨げる!)
- 慢性疲労(腸内環境の悪化で、体内の活性酸素が増加!)
- イライラ(セロトニンの分泌が低下し、興奮物質が暴走!)
- 無気力・うつ(セロトニンが過剰に分泌し、興奮物質が抑制!)
- 過敏性腸症候群(セロトニンの過剰分泌で、ぜん動運動に異常発生!)
- 花粉症などのアレルギー(腸内細菌のバランス悪化で、免疫機能が低下!)
- 手足ロ病などの感染症(免疫機能が低下し、外敵を攻撃しなくなる!)
- SIBO(小腸内細菌増殖症)(小腸内で細菌が大増殖し、ガスが大量発生!)
- がん(悪玉菌の増加で、有害な発がん性物質も増える!)
- 認知症(アルツハイマー型)⇒(腸内細菌の多様化が失われ、脳に原因物質が蓄積!)
- 高血圧(乳酸菌の減少による自己免疫で血管を傷つける!)
- 動脈硬化(アテローム性)⇒(腸内細菌の代謝物によって、血管にコレステロールが沈着!)
- 糖尿病(腸が脂肪肝をつくり、やがて高血糖へとつながる!)
便秘(運動不足や強いストレスで、腸の動きが「低下」!)
【原因】運動不足や強いストレス ←【対策】生活習慣や食生活を改善
↓
大腸のぜん動運動が弱くなったり、けいれんしたりする ←【対策】マッサージや運動で刺激!
↓ ←【対策】毎朝トイレに5分間!
便を先に送れず、水分をどんどん吸収
【結果】大腸の動きが悪いうえに、便が硬くなり排便しづらい。

下痢(腸の動きが「過剰」に活発になって、水分吸収が不十分に!)
【原因】強いストレスや消化不良、水あたり、冷え ←【対策】暴飮暴食を控え、生活習慣を改善
↓
大腸のぜん動運動が強くなり、水分分泌も増加 ←【対策】食生活の改善や運動などでリフレッシュ
↓
大膓内を急速に通過するため、水分を吸収しきれない←【対策】ひどい場合は下癪止め薬を使用
↓
【結果】便の水分量が多くなり、下痢や軟便になってしまう

食欲不振(ストレスや腸の不調が、満腹中枢を刺激!)
【原因】
①強いストレス
②便秘・下痢や過剰なガスの発生 ←【対策】食生活の改善
↓↓
①交感神怪が過剰にはたらく ←【対策】マッサージや運動をする
②腸管神経がSOSを発信
↓↓
視床下部の満腹中枢を剌激し、胃のふくらみも悪くなる
↓
【結果】食欲がなくなる

肥満(「太らせ薗」の増殖で、栄養素を過剰に吸収!)
【原因】高カロリー食を習慣的に食べる ←【対策】食生活を改善
↓
腸内で栄養素を吸収しすぎる細菌ファーミキューテスが増える
↓ ←【対策】運動をする
↓ ←【対策】食物繊維や発酵食品を食べ、やせ菌(バクテロイデス)を増やす
余分なエネルギーが増え、脂肪として取り込む量が増加
↓
【結果】脂肪過多の体型になる
(その他、メタンガスが発生しやすい人は肥満傾向で、メタボの人が多く、便秘が多いことが判明している。
水素ガスが発生しやすい人は、やせ型で下痢が多い。)

生理痛(腸内環境の悪化と女性ホルモンの分泌低下!
【原因】腸内細菌が多様性を失う ←【対策】食生活の改善
↓
腸内環境の悪化で女性ホルモン「エストロゲン」が減少 ←【対策】大豆を食べてイソフラボンを補給
↓
女性ホルモン効果のある物質エクオールを腸内細菌がつくれない
↓
【結果】月経前症候群(PMS:premenstrual syndrome)や更年期症状がひどくなる(肌荒れにも影響)

肌荒れ(悪玉菌増加で有害物質が肌に蓄積!)
【原因】腸内で悪玉菌が増加 ←【対策】生活習慣の改善
↓
悪玉菌がたんばく質をエサに有害物質フェノール類をつくり出す ←【対策】プロバイオティクスで乳酸菌を補給
↓
フェノール類が血流にのって全身へ送られる
↓
【結果】フェノール類が肌に到達し、肌荒れを引き起こす

むくみ・冷え性(悪玉菌の増加によって血行不良が発生!)
【原因】運動不足や長時間の姿勢維持 ←【対策】運動をする
↓
腸内の悪玉菌が増加 ←【対策】プロバイオティクスが有効
↓
便秘や下痢を起こし、腸の血流やリンパが滞る ←【対策】マッサージをする
↓
【結果】血行不良を起こし、手足や顔がむくんだり、手足が冷える

腰痛(腸管神経のSOSが周辺筋肉を緊張させる!)
【原因】強いストレスや生活習慣の乱れ ←【対策】セロトニンを増やす
↓
腸内環境のバランスが乱れる ←【対策】運動をする
↓
腸が腸神経系を通して不調のSOSを発信
↓
【結果】腰周辺の筋肉や皮ふを緊張させ、痛みが生じる
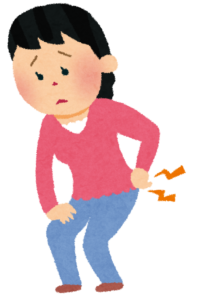
肩こり(腸のSOSが不良姿勢を招いて肩の負担増!)
【原因】強いストレス ←【対策】セロトニンを増やす
↓
腸内の不調を引き起こす ←【対策】運動をする
↓
腸神経系を通じてSOSを発信
↓↓
↓腹部の痛みや張りから姿勢が乱れる ←【対策】マッサージをする
↓↓
【結果】肩周辺の筋肉が緊張し、コリが生じる

不眠(腸内の不調が自律神経を乱し、睡眠を妨げる!)
【原因】①強いストレスや生活習慣の乱れ ←【対策】セロトニンやメラトニンを増やす
↓
腸内環境が悪化
↓ ←【対策】生活習慣を改善
腸神経系を通じて自律神経が乱れる
↓
【結果】交感神経が過剰にはたらいたり、就寝時間以降も消化作業が続いたりしたせいで不眠になる
↑
【原因】②遅い時間に脂肪の多い食事をとる ←【対策】しじみ汁等を飲む

慢性疲労(腸内環境の悪化で、体内の活性酸素が増加!)
【原因】運動不足や座りっぱなしの生活 ←【対策】運動をする
↓ ←【対策】筋トレも有効
腸内環境が悪化
↓ ←【対策】サラダチキンを食べる
体内の活性酸素が増加
↓
【結果】疲れやすくなる

イライラ(セロトニンの分泌が低下し、興奮物質が暴走!)
【原因】腸内環境が悪化
↓
幸せホルモン「セロトニン」の分泌が減少 ←【対策】生活習慣を改善
↓ ←【対策】運動で自律神経を整える
興奮をうながすドーパミンやノルアドレナリンが暴走する
↓
【結果】ちょっとしたストレスに怒りを抑えられなくなる ←【対策】ゆらぎでカラダのリズムをコントロール

無気力・うつ(セロトニンが過剰に分泌し、興奮物質が抑制!)
【原因】強いストレス
↓
神経伝達物質セロトニンやストレスホルモン(CRF) が過剰分泌 ←【対策】運動をする
↓ ←【対策】質のよい睡眠をとる
興奮をうながすドーパミンやノルアドレナリンのはたらきが低下
過敏性腸症候群も招く
↓
【結果】行動する意欲が生じにくくなり、うつにもなりやすい
※CRF(コルチコトロピン・リリーシング・ファクター)・・・ストレスホルモンのひとつで、過敏性腸症候群や機能性ディスペプシア(原因不明の慢性的腹痛)の病態に影響。
CRFのはたらきを抑えると、過敏性腸症候群の症状が改善することも動物実験て確認されている。

過敏性腸症候群(セロトニンの過剰分泌で、ぜん動運動に異常発生!)
【原因】強いストレス ←【対策】SIBOも原因と考えられる
↓
神経伝達物質セロトニンやストレスホルモン(CRF) が過剰分泌 ←【対策】セロトニンのはたらきを抑える薬
↓ ←【対策】便秘やガスの貯留感には運動・マッサージが有効
腸のぜん動運動に変調が現れる
↓
【結果】下痢・便秘になり、腹痛・張り・ガスの貯留感などを感じる

花粉症などのアレルギー(腸内細菌のバランス悪化で、免疫機能が低下!)
【原因】腸内細菌のバランスが悪化 ←【対策】食生活・生活習慣の改善
↓
腸管免疫系の機能が低下し、リ-キーガット症候群にもなりやすい ←【対策】プロバイオティクスが有効
↓
本来はOKな物質が病原性の細菌と認識される
↓
【結果】免疫細胞の防御反応としてアレルギーが発生

手足ロ病などの感染症(免疫機能が低下し、外敵を攻撃しなくなる!)
【原因】腸内細菌のバランスが悪化 ←【対策】食生活・生活習慣の改善
↓
腸管免疫系の機能が低下 ←【対策】プロバイオティクスが有効
↓
病原性の細茵が外敵として認識されない
↓
【結果】免疫細胞に攻撃されない病原菌が増殖

SIBO(小腸内細菌増殖症)(小腸内で細菌が大増殖し、ガスが大量発生!)
【原因】小腸の機能が低下したり、バウヒン弁がゆるんだりし、小腸内の細菌が大増殖
↑【対策】食生活・生活習慣の改善
↓
メタンガスや水素ガスが大量に発生 ←【対策】病院でSIBOの検査を受ける
↓ ←【対策】低FODMAP食を食べる
小腸の粘膜が壊され、有害物質などが血管内に流出
↓
【結果】下痢・便秘、うつ、肌荒れ、腹痛などさまざまな問題が起きる
SIBO=小腸内細菌異常増殖症(small intestinal bacterial overgrowth)

がん(悪玉菌の増加で、有害な発がん性物質も増える!)
【原因】腸内環境の悪化
↓
有害物質の生成。ホルモンの分泌異常。
↓ ←【対策】運動をする。食生活・生活習慣の改善。
各臓器に有害物質が送られたり、ホルモンの機能が不十分な状態に
↓
【結果】がん細胞の増殖スイッチがONに

認知症(アルツハイマー型)⇒(腸内細菌の多様化が失われ、脳に原因物質が蓄積!)
【原因】腸内細菌が多様性を失い、ディスバイオシスの状態に
↑【対策】週3~4回軽い運動をする
※ディスバイオシス:偏った食事や運動不足などの影響で、腸内細菌の種類の多様性が失われること。
↓
脳神経細胞にアミロイドたんばくが蓄積 ←【対策】緑黄色野菜、果物、魚などを腹7分目で食べる
↓
脳神経細胞が壊される
↓
【結果】大脳皮質が萎縮してしまう
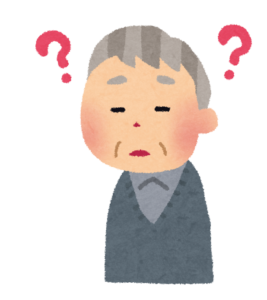
高血圧(乳酸菌の減少による自己免疫で血管を傷つける!)
【原因】習慣的な高塩分食の摂取 ←【対策】食生活の改善
↓
腸内の乳酸菌の一種ラクトバチルス・ムリヌスが減少 ←【対策】乳酸菌を補給
↓
Th17というリンパ球が過剰にはたらき、自己免疫で血管を傷つける
↓
動脈硬化を招く
↓
【結果】高血圧の症状を起こす
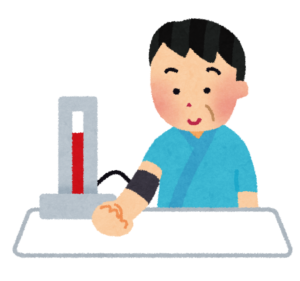
動脈硬化(アテローム性)⇒(腸内細菌の代謝物によって、血管にコレステロールが沈着!)
【原因】赤身肉などを多く食べる ←【対策】食生活の改善
↓
腸内細菌の代謝によってTMAO*という化学物質が生じる
↓ ←【対策】軽い運動をする
免疫細胞がコレステロールを取り込み、粥状になる
↓
【結果】粥状の沈着物がたまり、動脈硬化を招く
※TMAO:トリメチルアミン-N-オキシド(trimethylamine N-oxide)
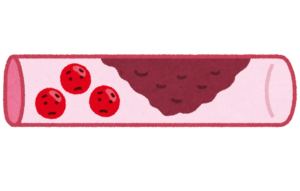
糖尿病(腸が脂肪肝をつくり、やがて高血糖へとつながる!)
【原因】飽和気味の食生活 ←【対策】食生活の改善
↓
限度超えの糖分が腸から肝臓に送られ、脂訪肝に ←【対策】運動をする
↓
高血糖の状態が続き、血糖を抑えるインスリンを分泌しても効かなくなる
↓
細胞内に糖を取り込めず、飢難状態に
↓
【結果】糖尿病と診断される

以上!おつかれさまでした!!
【重要】
このブログの内容は、ネット上の記事や書籍の抜粋&意訳を元にした個人の感想・戯言であり、なんら特定の物質の効能・効果を示すものではありません。